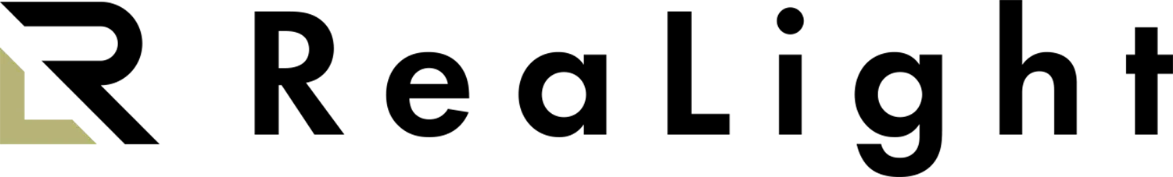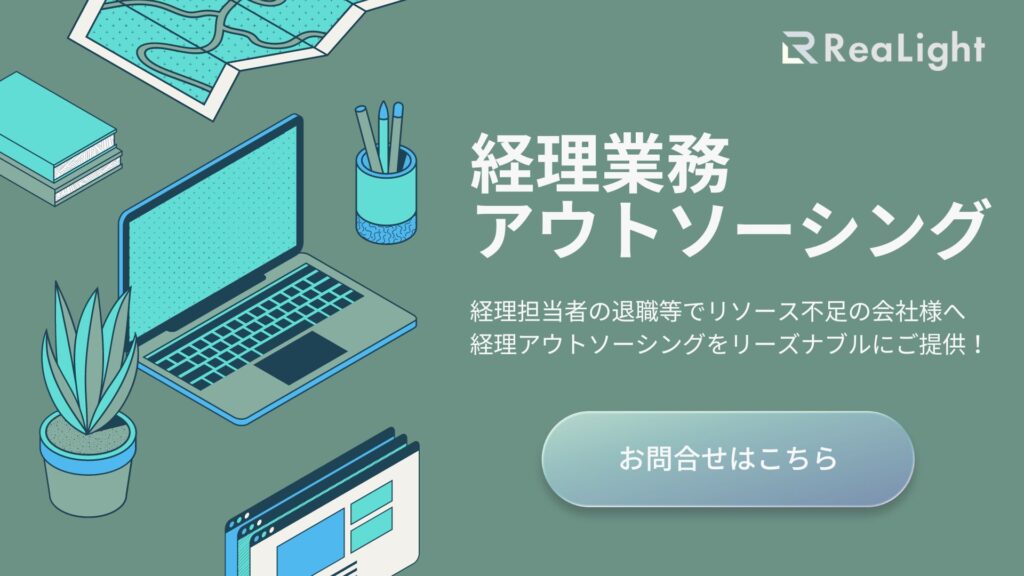新リース会計基準が2024年9月に公表され、2027年4月以後開始する事業年度から適用されることになりました。これまでオペレーティングリースとして賃貸借処理していた契約も、原則としてすべてオンバランス(貸借対照表に計上)することが求められるようになります。
本記事では、新リース会計基準の概要や背景、企業の財務諸表への影響、そして実務上の対応ポイントについて解説します。経理担当者の方はもちろん、財務諸表を読む立場の方も、ぜひ参考にしてください。
新リース会計基準とは?

新リース会計基準とは、企業会計基準委員会(ASBJ)が2024年9月に公表した、リース取引に関する新しい会計基準のことです。国際的な会計基準との整合性を図りながら、リース取引の経済的実態をより適切に財務諸表に反映させることを目的としています。
新リース会計基準について理解するために、以下の点を順に見ていきましょう。
- リース会計基準の歴史
- リース会計基準が改正された背景
- 新リース会計基準が公表された時期
ぜひ、全体の概要を掴む参考にしてください。
(1)リース会計基準の歴史
リース会計基準は時代とともに進化してきました。主な変遷を表にまとめると、以下のとおりです。
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1993年 | 日本で初めてリース会計基準が制定される |
| 2007年 | 当時の国際的な会計基準に合わせるため、日本のリース会計基準が改正。ファイナンスリースのオンバランス化が進む |
| 2016年 | 国際会計基準であるIFRS第16号が公表され、借手のすべてのリースをオンバランスする方針が示される |
| 2024年9月 | 国際的な会計基準との違いをなくすため、日本の新リース会計基準が公表される |
| 2027年4月 | 新リース会計基準の強制適用が開始 |
当初のリース会計基準では、ファイナンスリースとオペレーティングリースを区分し、ファイナンスリースは売買取引(オンバランス)として、オペレーティングリースは賃貸借取引(オフバランス)として処理していました。売買取引が原則でしたが、ファイナンスリース取引のなかでも所有権が移転しないものは賃貸借取引としての処理も認められていたため、多くの企業がこの方式を採用していました。
そこで2007年の改正では、所有権移転外ファイナンスリースの例外処理が廃止され、原則としてオンバランス処理が求められるようになります。しかし、オペレーティングリースについては引き続き賃貸借処理(オフバランス)が認められていたため、国際的な会計基準との差異が生じていました。
そのため、2016年にIFRS16号が公表され、オペレーティングリースを含み、全ての借手のリース契約を原則オンバランスとする方針が決定しています。これにより、再び生じてしまった国際的な会計基準との違いを解消するために公表されたのが、日本の新リース会計基準というわけです。
(2)リース会計基準が改正された背景
新リース会計基準への改正には、主に以下に挙げた3つの背景があります。
1つ目が、企業がオペレーティングリースを活用して財務諸表を意図的に軽く見せることが可能だったという問題です。特に航空会社や小売業など、多額のリース取引を行う企業では、オペレーティングリースとして処理することで、貸借対照表上に多額の負債を計上せずに済んでいました。
2つ目が、投資家や監査法人からは「リース取引の実態が財務諸表に正しく反映されていない」との批判が増加したことです。実質的には長期間の使用権と支払義務があるにもかかわらず、それが貸借対照表に表れないことで、企業の財政状態が適切に表示されていないという指摘がありました。
3つ目が、国際財務報告基準(IFRS)と日本基準の整合性を取るため、会計基準の見直しが必要となったことです。海外投資家が日本企業の財務諸表を理解しやすくするためにも、国際的な基準との差異を減らすことが求められていたのです。
このような背景から、リース資産の実態をより正確に反映するために、「使用権資産」と「リース負債」としてバランスシートに計上するルールへ変更されることになりました。
(3)新リース会計基準が公表された時期
新リース会計基準は2024年9月13日に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表されました。企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」および企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」として公表されています。
この新基準は2027年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになっており、2025年4月1日以後開始する事業年度からの早期適用も認められています。
3月決算企業の場合、2028年3月期(2027年4月~2028年3月)から強制適用となりますが、準備期間を考えると、早めの対応を検討しておくと安心です。リース契約の洗い出しやシステム対応など、実務上の準備に時間がかかることが予想されるからです。
新リース会計基準の公表から適用までには約2年半の準備期間が設けられていますが、会計処理の変更だけでなく、契約管理や業務プロセスの見直しも必要です。
新リース会計基準の概要

新リース会計基準は、リース取引の会計処理を大きく変更するもので、主に借手側の会計処理に大きな影響があります。ここでは、以下の点について詳しく解説します。
- 借手の会計処理について
- 貸手の会計処理について
- リースの定義について
- リースの識別について
- 適用時期について
それぞれ見ていきましょう。
(1)借手の会計処理について
新リース会計基準における借手の会計処理の変更点は、原則として、これまでオペレーティングリースとして賃貸借処理していた取引も含めて、すべてのリース取引をオンバランス(貸借対照表に計上)することが求められる点です。
旧基準では、オペレーティングリース契約の場合、毎月のリース料を費用として計上するだけで、資産・負債として計上する必要はありませんでした。これに対し、新基準では、すべてのリース契約について「使用権資産」と「リース負債」としてバランスシートに計上する必要があります。
- リース開始日にリース料総額の現在価値を「リース負債」として計上
- 同額を基本として「使用権資産」を計上
- リース負債については利息法により利息費用を計上しながら返済
- 使用権資産については減価償却を行う
例えば、月額10万円のオフィス賃貸契約(5年契約)がある場合、旧基準では毎月10万円を賃借料として費用計上するだけでした。しかし新基準ではリース契約の開始日にリース料総額の現在価値を計算し、その金額を「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上します。具体的には、リース料の支払額(この場合60か月×10万円=600万円)を適切な割引率で現在価値に割り引いて計算します。例えば、年利5%を適用した場合、現在価値は約532万円となり、この金額を使用権資産とリース負債として計上します。毎月の支払いは利息費用とリース負債の返済にわけて処理されます。リース負債は利息法に基づき利息費用が計上され、使用権資産は減価償却されます。
(2)貸手の会計処理について
貸手の会計処理については、基本的に現行のリース会計基準が踏襲されますが、以下に挙げた4つの変更点があります。
1つ目が、新リース基準適用対象の拡大です。リースの定義が変更されたことで、従来リースと認識されなかった契約もリースとして扱われる可能性があります。例えば、特定の設備を使用する権利を含むサービス契約なども、リースに該当する可能性があります。
2つ目が、収益認識会計基準との適用範囲の整理です。リース取引とその他の収益取引を明確に区分する必要があり、契約に含まれるリース部分と、非リース部分(サービス等)を分離して会計処理することが求められます。
3つ目が、「貸手のリース期間」の選択肢が設けられたことです。国際的な会計基準と同じく、借手のリース期間と同様に決定する方法と、現行リース基準の定めを実質的に受け継いだ解約不能期間をベースとする方法の2つが認められています。
4つ目が、ファイナンス・リースの第2法(リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法)の廃止です。収益認識会計基準との整合性を図るための変更となります。
(3)リースの定義について
新リース会計基準では、リースの定義が「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」と定められています。この定義により、「リース」と認識される契約の範囲が広がりました。
出典:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」
一定期間、対価を払って資産の使用権を得る契約は、「リース」と明記されていない契約書の場合も、リースとして扱われることが多くなります。例えば、「設備リース」「車両リース」「IT機器リース」だけでなく、オフィス賃貸契約や不動産賃貸借契約、さらには一部のサービス契約や業務委託契約の中にもリースが含まれる可能性があるのです。
場合によっては、特定のサーバーを使用するクラウドサービス契約や、特定の設備を使用する業務委託契約なども、条件によってはリースに該当する可能性があります。そのため、企業は保有するすべての契約を見直し、リースに該当するかどうかを判断する必要があります。
(4)リースの識別について
新リース会計基準では、契約がリースを含むかどうかを判断するための「リースの識別」に関する定めが新たに設けられました。
リースの識別の基本的な考え方は、契約において「特定された資産」が存在し、その資産の使用を「支配」しているかどうかで判断します。具体的には、以下の条件を満たす場合にリースと判断されます。
- 特定された資産が存在する(供給者が資産を自由に入れ替えられない)
- 資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利がある
- 資産の使用を指図する権利がある
出典:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」
また、1つの契約内にリース部分と非リース部分(サービス等)が含まれる場合、原則として分離して会計処理する必要があります。例えば、IT機器のリース契約に保守サービスが含まれる場合、保守サービス部分はリース負債には計上せず、通常の費用として処理します。
ただし、実務上の負担を軽減するため、リース部分と関連する非リース部分を合わせてリースとして処理することも認められています。この選択は、原資産のクラスごとに行うことができます。
(5)適用時期について
新リース会計基準は、2027年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。また、2025年4月1日以後開始する事業年度からの早期適用も認められています。
3月決算企業の場合、2028年3月期(2027年4月~2028年3月)から強制適用となりますが、準備期間を考えると、早めに対応を検討しておくと良いでしょう。
通常、適用初年度においては会計方針の変更として取り扱い、原則として過去の期間すべてに遡及適用します。ただし、適用初年度の期首の利益剰余金に累積的影響額を加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することも認められています。
また、実務上の負担を軽減するため、以下の経過措置が設けられていることも知っておくと便利です。
- 適用初年度前に契約した取引についてリースの識別を再度行わないことを選択できる措置
- オペレーティングリースだった取引について簡便的な方法でオンバランスすることを認める措置
新リース会計基準の適用には、契約の洗い出しやシステム対応など、実務上の準備に時間がかかることが予想されるため、早期に対応を始めることが重要です。
新リース会計基準の適用による財務への影響

では、準備を進めるためにも、新リース会計基準の適用が企業の財務諸表にどのような影響を与えるのかについて見ていきましょう。
新リース会計基準の適用は、企業の財務諸表や経営指標に以下の2つの影響を与える可能性があります。
- 企業の財務諸表への影響
- 企業評価・信用格付けへの影響
それぞれ解説します。
(1)企業の財務諸表への影響
新リース会計基準の適用により、企業の財務諸表には以下のような影響が生じる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | リース資産とリース負債の計上により、総資産と負債が増加 |
| 損益計算書(P/L) | リース料の支払いが利息・元本返済に分かれるため、従来のリース費用計上とは異なる |
| キャッシュフロー(C/F) | オペレーティングリース費用が「営業キャッシュフロー」から「財務キャッシュフロー」に分類される場合がある |
| EBITDA(営業利益+減価償却費) | 増加による指標の変化 |
貸借対照表(B/S)への影響は、オフィスビルや店舗、工場などの不動産賃貸借契約や、多数の車両リース契約を持つ企業では大きくなる可能性があります。
また、利息費用は営業外費用として計上されるため、営業利益は増加する傾向にあります。ただし、経常利益や当期純利益への影響は、リース期間全体で見れば中立的です。
(2)企業評価・信用格付けへの影響
新リース会計基準の適用は、企業評価や信用格付けにも影響を与える可能性があります。クレジット評価機関が新基準適用後の財務データをどのように解釈するかによって、その影響も変化するからです。
例えば、リース負債の増加により、負債比率(D/Eレシオ)や自己資本比率などの財務健全性を示す指標が悪化する可能性があります。特に、多額のオペレーティングリース取引を行っている企業では、その影響が大きくなるでしょう。
また、ROA(総資産利益率)は、分母となる総資産が増加するため、一般的に低下する傾向にあります。一方、ROE(自己資本利益率)への影響は、リース期間や利益水準によって異なるでしょう。
なお、信用格付けへの影響については、格付機関は従来からのオペレーティングリースの影響を考慮して格付けを行っていることが多いため、大きな変化はないとの見方もあります。しかし、これまで考慮されていなかったリース取引が新たに認識されることで、一部の企業では格付けに影響が出る可能性は捨てきれません。
企業としては、新リース会計基準の適用による財務指標への影響を事前に把握し、必要に応じて投資家や金融機関に対して説明を行うことが重要です。また、財務制限条項(コベナンツ)が設定されている借入金がある場合は、新基準適用による影響を金融機関と協議しておくことも必要でしょう。
新リース会計基準に関するよくある質問

ここからは、新リース会計基準に関するよくある質問に回答します。
- 中小企業にも適用される?
- 短期リース(12か月未満)の場合はどうなる?
- リース契約の更新時に追加対応は必要?
- 監査法人とのやりとりで注意すべき点は?
ぜひ、参考にしてください。
(1)中小企業にも適用される?
中小企業については、「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」に準じて会計処理を行うことが一般的であり、新リース会計基準の強制適用対象とはなりません。
新リース会計基準の適用対象は、主に上場企業や会計監査人を設置している会社(大会社)とその子会社・関連会社です。具体的には、以下の企業が対象となります。
- 金融商品取引法の適用を受ける企業(上場企業など)とその子会社・関連会社
- 会社法上、会計監査人を設置する企業とその子会社
ただし、親会社が上場企業である場合、その子会社は規模にかかわらず新リース会計基準の適用対象となります。連結財務諸表作成のために、グループ内で統一した会計処理が求められるためです。
(2)短期リース(12か月未満)の場合はどうなる?
新リース会計基準では、実務上の負担を軽減するため、短期リースや少額リースについては簡便的な取扱いが認められています。原則として定額法により、使用権資産とリース負債を計上せず、リース期間にわたってリース料を費用として計上できます。
ただし、契約期間が12か月以内でも、延長オプションを行使することが合理的に確実である場合は、その期間も含めてリース期間を判断するため、短期リースに該当しない可能性があります。
また、少額リースについても同様の簡便的な取扱いが認められています。少額リースには、以下の2つの基準があります。
- 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料が当該基準額以下のリース
- 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース(リース料総額300万円以下)または新品時の原資産の価額が少額であるリース(5,000米ドル以下を念頭)
出典:公益社団法人リース事業協会「新リース会計基準について-借手側の会計処理-」
この簡便的な取扱いを適用することで、すべてのリース契約をオンバランスする負担を軽減できます。
(3)リース契約の更新時に追加対応は必要?
リース契約の更新時には、新リース会計基準にもとづいて会計処理を見直す必要があります。
まず、契約更新がリースの契約条件の変更に該当するかどうかを判断してください。リースの契約条件の変更とは、「リースの契約条件の変更」とは、リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更(例えば、1つ以上の原資産を追加若しくは解約することによる原資産を使用する権利の追加若しくは解約、又は、契約期間の延長若しくは短縮)を指します。
出典:公益社団法人リース事業協会「新リース会計基準について-借手側の会計処理-」
契約更新がリースの契約条件の変更に該当する場合、以下のいずれかの処理を行います。
- 変更前のリースとは独立したリースと見なして会計処理を行う(原資産を使用する権利の追加があり、その対価が独立価格に見合う場合)
- リース負債の計上額を見直す(上記以外の場合)
リース契約の更新時にはさまざまな判断と会計処理の見直しが必要となるため、契約管理と会計処理の連携が重要になります。
(4)監査法人とのやりとりで注意すべき点は?
新リース会計基準の適用にあたり、監査法人とのやりとりでは以下の点に注意が必要です。
- どのような契約をリースとして識別するか
- 判断プロセスや基準はどうなっているか
- リース期間の決定方法はどうなっているか
- 延長オプションや解約オプションをリース期間に含めるか
- 割引率の設定方法はどうするか
- 新リース会計基準の適用による財務諸表への影響はどうなるか
- 新リース会計基準の適用に関する開示内容はどうするか
- 適用初年度の注記事項や経過措置の適用状況はどうなるか
監査法人とのコミュニケーションを密に取りながら、計画的に新リース会計基準への対応を進めることが重要です。
新リース会計基準への対応に不安がある場合はReaLightへ
新リース会計基準は、企業の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある重要な会計基準の変更です。特にリース取引が多い企業では、資産・負債の増加や各種財務指標への影響が大きくなることが予想されます。
新リース会計基準への対応には、リース契約の洗い出しから会計処理方針の策定、システム対応、開示内容の検討まで、多岐にわたる準備が必要です。しかし、多くの企業では、リース契約の管理体制が十分でなかったり、会計処理の知識が不足していたりするため、対応に苦慮しているケースも少なくありません。
ReaLightでは、公認会計士を中心としたプロチームが、新リース会計基準への対応をトータルでサポートします。契約の洗い出しから影響度分析、会計処理方針の策定、システム導入支援まで、企業の状況に応じた最適なソリューションを提供します。
新リース会計基準への対応でお悩みの方は、ぜひReaLightにご相談ください。経理業務の専門家が、貴社の状況に合わせた最適な対応策をご提案します。